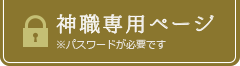由 緒
祭神新田義貞公の戦歿地は元福井市新田塚の燈明寺畷と伝えられている。
明暦年間(1655~58)此の地から新田義貞所用のものと思われる兜を発掘したので万治3年(1660)福井藩主松平光通公はそこに「新田義貞戦死此所」と刻した石碑を建て、明治3年同松平茂昭公が同地に一祠を建立し、公を奉斎する官幣社の創建方をその筋に建議した。
そこで同9年11月燈明寺畷の祠は別格官幣社に列せられ藤島神社の社名を賜わり、新田義貞公を主神として、新田義宗卿脇屋義助卿を配祀せらるる旨仰出された。
12月15日同地の仮殿落成したので、勅使桐山純孝を遣わし御霊代を鎮安せしめられた。
ここで始めて朝廷の祭祀を行わせられ、次いで同11年1月10日新田義顕卿同義興卿以下殉難将士を配祀せられる旨仰せ出された。
明治14年11月23日燈明寺畷を南に距る12丁余福井市牧ノ島に社殿新に造り遷座祭を行った。
ところが同社地一帯は卑湿の地であり、当時九頭龍川の改修成らず、降雨に際し水害頻りに起こり、恐れ多くも濁水神域を汚し奉ること一再に止まらない状態であった。
それで同31年4月15日現在地を卜定せられ移転することとなり奉遷会を組織し侯爵松平康荘を会長とし、全国官民有志協力して遂に同34年5月22日社殿境域の工を竣り遷宮祭を行った。
神殿以下諸建物の設計は工学博士伊藤忠太、図案は古社寺特別造物保存調査員案藤時蔵の考案、島田藤吉これが工事に従った。
昭和20年7月19日戦災の為炎上御本殿以下主要建造物を失い、次いで昭和23年6月28日福井大震災の為残りの建物も崩壊し去ったが昭和31年御創立80周年を記念して復興奉賛会を組織し、高松宮殿下を名誉総裁と仰ぎ松平康昌を総裁に熊谷太三郎を会長として再建に当り翌昭和32年11月12日竣工式を行った。
次いで昭和50年5月御鎮座100年祭には宝物収蔵庫を兼ねた総合結婚式場藤寿殿寛政、昭和63年8月義貞公御殉節650年祭斎行に当り記念事業として御本殿内陣の改装と神符授与所を新築し、又新に本殿玉垣を新設併せて境内玉垣も増設するなど境内の整備を行い漸く災害前の姿にまで復興した。
当神社は御創立以来皇室の御崇敬厚く、御祭神に対する御贈位又は御物の御寄進一再に止まらず、本県下への行幸啓の節或は皇室国家の重大事に際してはその都度勅使を遣され奉幣されている。
即ち明治9年12月15日新田義貞公に対し正三位、同15年には正一位を贈らる。
同11年明治天皇本県行幸勅使奉幣。
同16年脇屋義助に対し従三位、同42年義宗、義顕、義興に対し従三位を贈らる。
同37年日露の役に際し勅使奉幣。
大正4年11月大嘗祭の為勅使奉幣。
同13年皇太子本県行啓に際し奉幣。
昭和3年大嘗祭の為勅使奉幣。
同8年特別大演習の為行幸御参拝奉幣し給う。
同13年義貞公御殉節600年祭に際し祭粢料を下賜。
各宮家より幣帛あり。
同22年陛下北陸行幸に際し幣帛料を賜う。
同31年創立80周年祭には高松宮御台臨・
同32年神殿竣工祭にも高松宮御台臨。
同50年創立100年祭には高松宮及同妃殿下御台臨。
同63年8月義貞公御殉節650年大祭には畏き辺りより祭粢料を賜う。